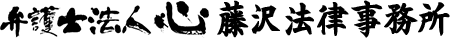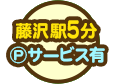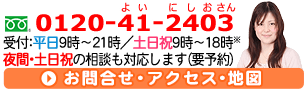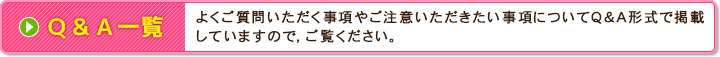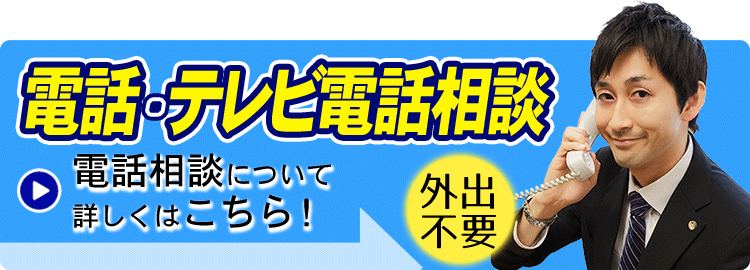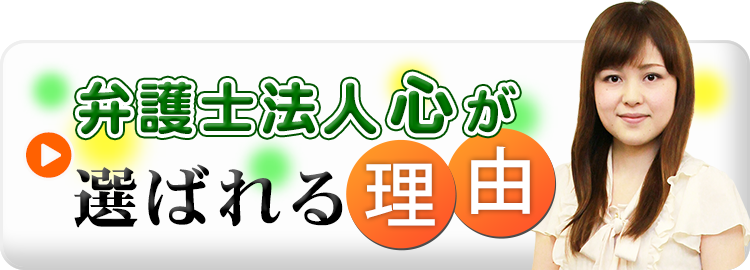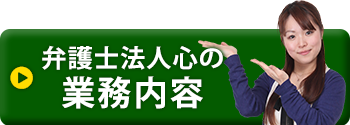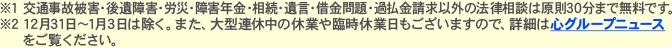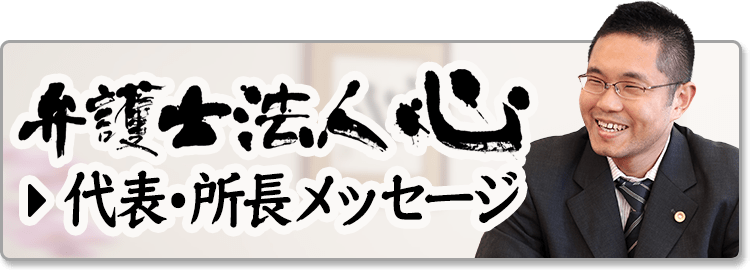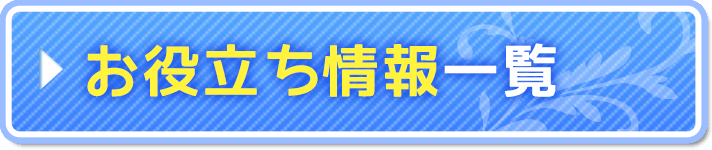相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割はどうするのか
1 相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割ができない
認知症で判断能力が低下している方がいる場合、財産内容や権利関係についてわからず、必要な書類について署名押印もできないため、遺産分割を行うことができません。
そうすると、事実上手続きが進められず、預貯金の解約や不動産の登記などを行うこともできなくなってしまいます。
このような判断能力が低下した方の権利を守るために、成年後見制度があります。
2 成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類がある
法定後見は、本人の判断能力の低下具合などにより、後見・保佐・補助の3つの類型があり、最も低下している場合が後見です。
後見の場合を例にとると、家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人を選任してもらえば、その成年後見人が認知症の本人に代わり、遺産分割を行うことができます。
これに対し、任意後見は、自分の判断能力が衰えてきたときに備えて、本人があらかじめ後見人を選び、代わりにしてもらいたい内容について決めておくことができるという制度で、公正証書で任意後見契約を締結するものとされています。
認知症の相続人に任意後見人がついている場合は、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じ、遺産分割を行うことができます。
3 成年後見制度のデメリット
前述のとおり、成年後見制度により、本人の権利が守られるのですが、申立てのために必要な書類を収集したり、申立書を作成するために、時間や費用がかかるため、親族などの関係者のうち誰がそれを行うのかという問題があります。
また、成年後見人がいったん選任されると、遺産分割が終わってからも後見制度の利用が続きます。
成年後見人に弁護士や司法書士などの専門家が就く場合、家庭裁判所の決定により月額2万~10万円程度の報酬が発生し、本人の財産から支払われることになり、本人の財産が減ってしまうため、親族からするとその点を心配することもあると思われます。
なお、親族などが成年後見人に選任される場合でも、申立により報酬を得ることができますが、本人の財産が少ない場合などは申立てをしない場合もあり、基本的には後見制度の利用がずっと続くため、やはり誰が成年後見人になるのかという点が問題となります。
このようなことを検討したうえで、成年後見により、遺産分割を行うこととなります。