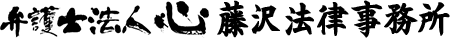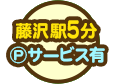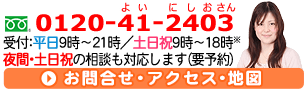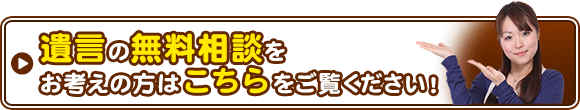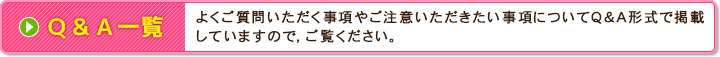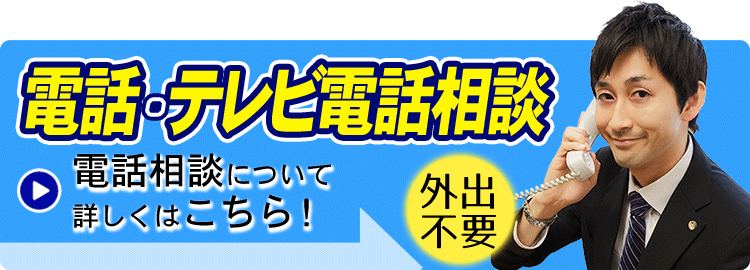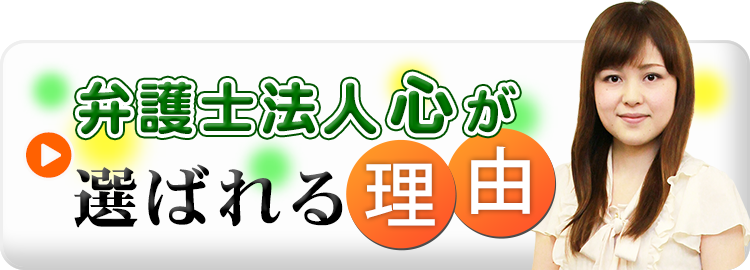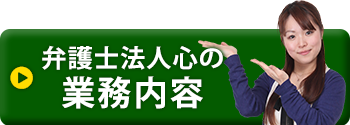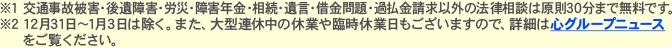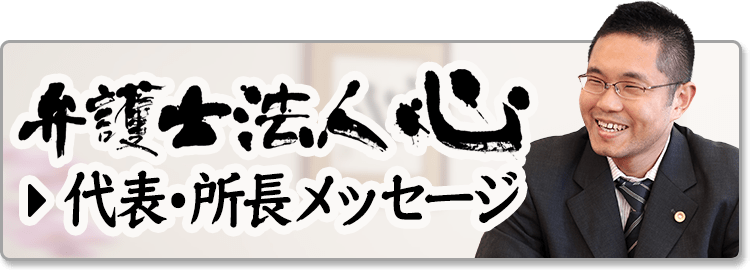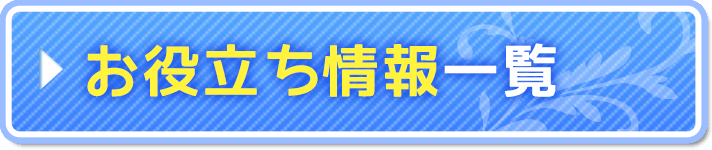公正証書遺言のメリット・デメリット
1 公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、公証役場の関与の下、遺言者が遺言を作成するものです。
公正証書遺言の場合、遺言書の作成にあたっては、公証人と証人2名が関与します。
公証役場において、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を筆記したうえで、遺言者と証人にその内容を読み聞かせ、又は閲覧させます。
その後、遺言者と証人が、公証人が作成した筆記が正確なことを承認し、各自遺言書に署名および捺印をします。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本が遺言者に交付されます。
2 公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の場合には、公証役場が関与することで遺言内容の正確性や有効性が担保されるので、自筆証書遺言と比較すると、相続発生後に相続人間でのトラブルを防止できる可能性があります。
公正証書遺言の場合、公証人および証人という第三者の関与の下で遺言が作成されますので、遺言者の遺言能力(遺言をすることができる能力)は一定程度担保されているといえます。
また、自筆証書遺言の場合、相続発生後に検認という手続きを行う必要がありますが、公正証書の場合は検認を行う必要がありませんので、相続開始後にすぐに遺言執行に着手できるのもメリットであるといえます。
3 公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットは、自筆証書遺言と比較すると作成するのに時間を要することに加え、作成にコストがかかるという点です。
公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人の立ち合いの下で作成されますので、準備が必要になります。
公証役場を予約し、公証人との間で遺言の内容について擦り合わせをすることになります。
そのため、自筆証書遺言と比較すると、簡便に早くに作成することができないといえるでしょう。
また、公正証書遺言を作成するのには次の①~⑥の費用がかかります。
公正証書遺言の作成にあたっては、相続人を確認するため①被相続人の戸籍と相続人の戸籍が必要になります。
②また、遺産に不動産がある場合、不動産の謄本・固定資産税評価証明書が必要になります。
③預貯金がある場合、通帳が無い場合には、残高証明書等の預貯金の残高が分かる資料も必要です。
④本人確認のために、被相続人の印鑑証明書も取得する必要があります。
これらの書類を取得するための費用がかかります。
また、公正証書遺言作成の際には、証人2名の立ち合いが必要です。
遺言者の推定相続人は証人になることはできません。
⑤弁護士や司法書士等の士業に依頼する場合や、公証役場の職員に証人を依頼する場合、証人一人につき概ね1万円前後の日当が発生することが多いです。
⑥さらに、公証役場への手数料も必要になります。
正証書遺言を作成する場合、公証役場に作成手数料を支払う必要があります。
この手数料は、公証人手数料令という政令によって全国一律で定められており、具体的な金額は遺産の金額によって異なります。